リバーライトさんをご紹介...鉄のフライパンができるまで
| 「焼く」「炒める」ことに関しては右に出るものはない「鉄のフライパン」。今回は日本を代表するフライパンメーカー・リバーライトさんを訪問し、取材させて頂いた。また鉄のフライパン作りを拝見した。 |  |
 |
リバーライトの工場長宇都宮氏は、熱い。ともかく熱い。情熱家だ。フライパンのことを質問したら、もう徹底的に教えてくれる。手加減がない。そして生き字引だ。知らないことはない。 今回リバーライトさんを訪問。社長の岡山氏にお会いした。男から見てもダンディで、渋くて、かっこいい。・・・そして「熱い」。語り始めると、フライパンへの情熱がほとばしる。自然とぐいぐい引き込まれていく。もしかしてこの「熱さ」はリバーライトさんのまぎれもないカラー、社風なのか。そうかもしれない。だってフッ素コートのフライパンが世界中を席巻しようとしているさなかに、木柄の付いた鉄のフライパンを売り始めたのだ。情熱がなくてはできない。なまじな語りでは、思いが伝わらない。 リバーライトさんの工場は千葉県印旛郡白井町にある。北総公団線の西白井駅が最寄りの駅だ。駅に着くと、工場長が迎えに来てくれた。ここは東京のベットタウンとして急成長している。しかし緑も多く、どこかのどかで、また計画的に整備されているので、ぎすぎすした感じがない。いい町だ。 |
| (左)リバーライト社長岡山氏 と工場長宇都宮氏 |
| (右)オフィスの壁に吊されたリバーライトさんのフライパンを中心とした調理道具達。こういうところにも、メーカさんの調理道具に対する深い愛情をみる。 |  |
 |
| 拡大 | 拡大 |
 |
(左)鉄をリボン状に巻いたロールから、フライパン達が生まれる。リバーライト社のフライパンは、黒色をしていない。一般的鉄のイメージである黒鉄板、その高温で焼けた表面の酸化被膜を洗い落とし、常温で調質圧延(プレス)し、整えたものだ。鉄生地本来の色、キメの細かさをもった鉄板だ。 |
 |
 |
 |
| ロール状の鉄板は、レベラーを通り、まっすぐな板に調整される。 そして丸く型抜きが行われる。 |
||
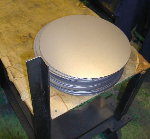 |
 |
(左)丸く打ち抜かれた鉄板。 まだフライパンの面影はない。 (右)そしてたくさんの鉄くず。 これはまた元の鉄へと復元される。良質の鉄くずだ。 |
 |
 |
| 「ちょっとだけこっちを向いてくださいね」 この時だけちょこっと笑顔をみせてくれた 職人の山盛氏。 |
平らな鉄板をフライパンの形状に 絞る作業の始まり。 滑らかに加工できるよう前もって絞り油を塗る。 |
 |
 |
 |
| プレスでの加工ではない。ダイヤモンドの次に固いのではないかと言われる超硬金属ローラーが、 軸に乗って回転する鉄板を、縁に向かって絞っていく。(スピニング絞り(回転絞り加工)) |
 |
 |
 |
| フライパンの縁はざらざら して危険な状態。 この機械はそのけばを取り除くもの。 丁寧に手作業で行われる。 |
持ち手を付ける為の 穴を開けている。 |
だいぶフライパンらしく なってきた。 |
 |
 |
 |
| 錆止め皮膜を塗り 乾かしている様子。 手で剥がせる塗膜。 |
焼きゴテでひとつひとつ ロゴを入れている。 創業当時から 変わらないやり方。 |
仕上がったハンドル。 |
 |
 |
| 持ち手を付けるための金具を リベット止めしてる。 |
組み立て。 私たちにも簡単にできる。 人に優しい仕様だ。 |
 |
 |
| 「皆様、こちらを気にせず、自然にお願いします。」 | 丁寧に箱詰めされる。 |